2013年に惜しまれながら逝った、著名映画評論家ロジャー・イーバートの人生を描いたドキュメンタリー『Life Itself/ライフ・イットセルフ』のレビューです。映画評論家として初めてピューリッツァー賞を受賞し、古今東西の映画に精通した博覧ぶりからアメリカで最も信頼される映画評論家でもあり、なおかつその手厳しさから恐れられもした人物。彼が終生失わなかった映画と人生への情熱を描いた珠玉のドキュメンタリー映画。
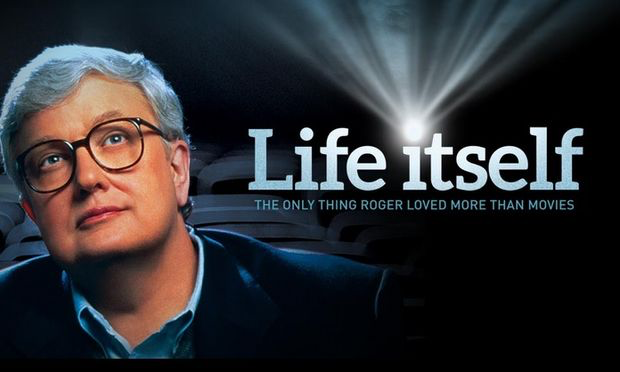
『Life Itself/ライフ・イットセルフ』
2014年全米公開/日本未公開
監督:スティーブ・ジェームズ
原作:ロジャー・イーバート著『Life Itself: A Memoir』
出演:ロジャー・イーバート、チャズ・イーバート(妻)、マーティン・スコセッシ、ヴェルナー・ヘルツォークなど
あらすじ
アメリカで最も信頼された映画批評家ロージャー・イーバートの生涯を、彼の自伝を基に、妻や友人、マーティン・スコセッシやヴェルナー・ヘツォークなどへのインタビューと合わせて描き出すドキュメンタリー。
1967年にシカゴ・サンタイムズの映画評を担当し、1975年には映画評論家としては初めてピューリッツァー賞を受賞。東海岸の大手新聞社からの誘いを断りシカゴに留まり、1976年ライバル紙だったシカゴ・トリビューンのジーン・シスケルと組んで映画批評番組を開始する。
時に辛辣な言葉で作品をこき下ろし、番組でタッグを組んだジーン・シスケルと衝突することもしばしばあった。
相棒のジーンを脳腫瘍で失った後、2002年ロジャー・イーバートは癌と診断されたことを公表。妻の支えのなかで度重なる再発と戦い、顎を切除して声を失っても彼は自身の信念と情熱を注ぎながら多くの映画を批評し続ける。
アメリカで最も信頼され恐れられもしたロジャー・イーバートの人生を、彼の映画への情熱とその証言を通して描いたドキュメンタリー映画。
レビュー
アメリカという国は挙げればきりがないほどの問題を抱えている。きっとその根深さで言えば、日本よりも深刻だろう。しかし少なくとも映画業界においてはその限りではない。映画会社の思惑とは無関係に、その作品の商業的可能性などには阿ることなく「観るべき映画」と「観るなくてもいい映画」を自身の信念と責任においてレクチャーしてくれる映画批評家が存在し、そして機能している。その象徴が2013年に惜しまれながら逝ったロジャー・イーバートだろう。
彼は日本で言えば淀川長治のような存在に近いだろうが、淀川が映画編集者から東宝などの映画宣伝部を渡り歩いたのに対しイーバートは新聞記者から映画批評家となっているためジャーナリストとしての気質が強く、気に入らない映画に対しての酷評ぶりはより激しいものがある。また「ファビュラス・バーカー・ボーイズ」を名乗っていた頃の町山智浩 氏と柳下毅一郎氏の活動は、ロジャー・イーバートとジーン・シスケルのタッグを意識したもので、特にイーバートの酷評スタイルから大きな影響を受けていることが伺える。
本作はイーバート自身が書いた半生記の『Life Itself: A Memoir』を基に、顎を摘出し声を失うも、50歳にして出会った生涯の伴侶の助けのなかで死を迎えるまでの彼の人生全体を、彼自身の闘病記録と親交のあった人々へのインタビューを通して描いている。そしてそこには常に彼の映画への情熱と無邪気なまでの頑固さが映し出されている。特に印象的なのがイーバート自身をアメリカを代表する映画批評家に押し上げたジーン・シスケルとの映画批評番組に関するパートだった。
シカゴを代表するトリビューンとサンタイムズは、前者が主にインテリ向けであるのに対しイーバートが在籍したサンタイムズは労働者や有色人種を主な読者層とするタブロイド。その紙面の違いはそのまま二人の映画批評スタイルにも表れている。イーバートは『俺たちに明日はない』を「我々の物語だ」と絶賛するなど反権力を象徴するような作品への強い共感を隠さない。『スカーフェイス』を退屈だと評したシスケルに対してイーバートが激しく抗議するシーンは特に印象的で、蓮實重彦氏の評に激高する町山氏の姿ともだぶる。そういった二人の批評家としての立ち位置の違いは、1970年公開で現在でもカルト映画として語られるラス・メイヤー監督作『ワイルド・パーティー』の脚本家としてイーバートが参加していた頃に、シスケルはまさにその映画のなかで描かれるような華やかで強欲な世界に属していたことも明らかになる。
無邪気を通り越した悪態をついて撮影を妨げるイーバートに向けてシスケルは「クソ野郎」と罵る。二人は相手の意見を尊重するとために自分の批評を曲げるようなことはなく、故にカメラの前でも度々衝突を繰り返す。しかし同時に二人は映画への情熱を通して硬く結ばれてもいた。シスケルにとってイーバートは「クソ野郎」であったことは間違いないが、同時にシスケルにとってイーバートは「私のクソ野郎」でもあった。だから99年にシスケルが脳腫瘍で亡くなった時イーバートは深く傷つき、それが彼の死生観を形づけることにもなる。タイトルからもわかるように映画が彼の「人生そのもの」だったことは、映画を通した人間関係のなかにも息づいているのだ。
シネフィル(映画狂)という言葉が主にジャンル映画への傾倒を指す言葉のようになったしまった昨今において、イーバートは本当の意味でのシネフィルだった。イングマール・ベルイマンやヴェルナー・ヘルツォークなどのヨーロッパ映画だけでなく、彼は日本映画も非常に高く評価されていて、小津の『東京物語』は生涯ベスト10にも選ばれ、他にもアニメにも目を向け『ポニョ』には4つ星が与えられ『千と千尋の神隠し』や『楢山節考』などは4つ星を超えた「偉大な映画」として評価されている。そして『ポニョ』評の中では「日本映画でアニメ」だからという理由で観ることを躊躇う人を「間抜け野郎」とさえ非難する。古今東西の映画に精通し、それらを分け隔てることなく愛する彼の姿勢は、実生活においても肌の色、宗教といった様々な違いさえも軽く飛び越えてしまう。
劇中でヘルツォークがイーバートを「戦士だ」と言い表した言葉が響く。彼は批評家として誰にも阿らなかったし、恐れもしなかった。結果多くの映画は血祭りにあげられ、興行にも影響を与えることになる。しかし彼の映画への分け隔てない愛情は、若く野心的な映画作家たちの拠り所にもなり、観客とっては頼るべき指針となる。クソみたいな映画はクソと言い放ち、評価されるべき映画はそれがインディペンデントだろうが大作映画だろうが外国映画だろうが平等に評価する。アメリカの映画ジャーナリズムの生育においてイーバートの存在は殊の外大きい。
政治腐敗とジャーナリズムの貧困が合わせ鏡で向かい会うことと同様に、ハリウッド映画の質もまたその批評性の健全さと同居している。もちろんイーバートがいたからハリウッドが素晴らしいというのではない。イーバートら批評家の意見を映画作品の表象として受け入れられる土壌がアメリカ社会に存在するということが重要なのだろう。
この作品を見ながら、翻って日本はどうだろうと自問せずにはいられなかった。もちろん日本にも優れた批評家は存在する。しかし彼らは日本映画界の表象として享受されているだろうか。正当に評価されているだろうか。テレビなどの一般にも影響力をもつマスメディアでも重宝されているだろうか。以前、テレビでもよく見かけるオタクの重鎮を自認する人物らによる対談の中で、「どんな映画もとにかく見続けるという態度はバカ」で「その上澄みだけをかすめるのが賢明」とする意見を読んでどうしようもなく情けなくなったことを思い出す。その文章を読んで10年ほど経った今、発言者の一人は女性問題とその態度で、もう一人は盗作問題で、批評者としては全く信頼に足らないことが明らかになった一方で、「バカ」と名指しされた映画批評家らは未だに信頼できる数少ない批評者であり続けている。しかしそれでも未だにメディアで重宝されているのは、岡田と唐沢の方だということは一体どういうことなのだろうか。
いい加減まとめに入ると、本作は一人の素晴らしい映画批評家の人生を描いた作品である。そしてそれ以上に一人の映画批評家の人生を描いた素晴らしい作品でもある。映画について語ることの本当の姿を描いた稀有な一作。作品と批評、それらは決して主従関係にあるのではなく、それぞれが独立した意思と情熱を持って語られるべきものであるということが本作にはしっかりと描かれている、まさにサムズアップな一作。
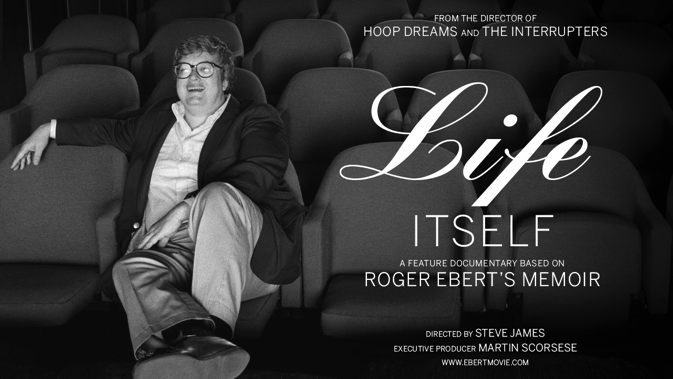
ということで『Life Itself』のレビューでした。残念ながらアカデミー賞のドキュメンタリー部門では候補から漏れてしまい、そのため日本でソフト化される可能性もかなり低くなってしまった作品ですが、それでもとても素晴らしい一作でした。2013年に彼が亡くなるまではイーバートの批評サイトを毎日のようにチェックしており、自分の意見と少しでも重なる部分があれば、なぜか褒められたようで小躍りしたりしていたため彼の死はそれなりにショックでした。このサイトでは映画レビューする際に星付けはしていませんが、今後よりしっかりとしたレビューが書けるようになったら、いつか挑戦してみたいものです。
この映画は一般の映画ファンも然る事ながら、映画を観ることよりもセレブと写真を一緒に撮ることに血眼になって海外の映画祭に参加している一部の関係者にこそ観てもらいたいですね。実際にそういうライターさんはいるんです
個人的には宝物のような一作。とにかくオススメです。
[ad#ad-pc]
参照サイト:Roger Ebert.com


コメント